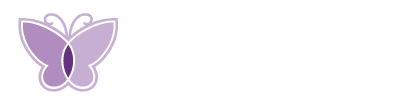熊本県のアンテナショップ、銀座熊本館(ぎんざ くまもとかん)は、東京の銀座にあります。
このアンテナショップは、1994年(平成6年)10月4日に営業を開始しました。熊本県は、比較的、他県よりも早い時期から東京でアンテナショップを展開しています。
アンテナショップの面積は、100㎡以上200㎡未満です。アンテナショップの1階では物産販売、アンテナショップの2階には観光案内と飲食施設があります。
熊本県アンテナショップの取扱い品目は、1000品目あります。
熊本県アンテナショップ、銀座熊本館を運営している熊本県東京事務所は、ホームページ、ブログ、フェイスブックでも情報発信を行っています。
今回、熊本県アンテナショップ、銀座熊本館を運営している熊本県東京事務所のご協力を得て熊本県アンテナショップの人気商品を取材させていただきました。熊本県アンテナショップ人気商品の取材記事は、別途掲載していきます。
| アンテナショップ | 熊本県 銀座熊本館 |
| Webサイト | http://www.kumamotokan.or.jp/ |
| 住所 | 東京都中央区銀座5丁目3−16 |
| 設立 | 1994年10月4日 |
| 事業内容 | 物産販売 飲食施設 観光案内 |
| 取扱い品目 | 1000品目 |
| 面積 | 100㎡以上200㎡未満 |
| インターネットの活用 | ホームページ ブログ フェイスブック |
| 調査日 | 2018年1月30日 |
(写真:熊本県 アンテナショップ 銀座熊本館 入口)
(写真:熊本県 アンテナショップ 銀座熊本館 1階)
熊本県PRマスコットキャラクター「くまモン」がいっぱい
熊本県アンテナショップ、銀座熊本館の2階に、多種類のくまモングッズが販売されています。
(写真:熊本県 アンテナショップ くまモン グッズ販売)
くまモンとは、
熊本県は、九州新幹線開業のPR活動に使用するマスコットキャラクター くまモンを2010年3月に発表しました。
くまモンは、九州新幹線開業までのキャンペーンキャラクターでしたが人気が出るにつれて、くまモンを熊本のPRに活用しようとする動きが高まり県の統一イメージキャラクターとなりました。
くまモン プロフィール
| 生まれたところ | 熊本県 |
| 誕生日 | 3月12日(九州新幹線全線開業の日) |
| 性別 | オスじゃなくて男の子! |
| 年齢 | ヒミツ(5歳というのは都市伝説) |
| 性格 | やんちゃで好奇心いっぱい |
| とくいわざ | くまモン体操とサプライズを見つけて広げること。 |
| お仕事 | いちおう公務員。 知事から熊本県の営業部長兼、しあわせ部長に抜擢。 くまもとサプライズを広めることで大好きな熊本の魅力をみんなに伝えるんだモン! |
| 出没するところ | だれかをハッピーにしたいという想いがあるところ |
くまモン オフィシャル ホームページ
熊本県 観光案内がいっぱい
熊本県アンテナショップの2階には、熊本県の観光案内所があります。
熊本の見所や、熊本のグルメガイドなどが分かります。
熊本の特産品 馬肉に関する情報もあります。
「西郷(せご)どん」に関連する熊本城 西南戦争(薩摩と政府軍の戦い)の観光スポット情報もあります。
(写真:熊本県 アンテナショップ 観光案内)
熊本県 アンテナショップの2階 飲食コーナー
(写真:熊本県 アンテナショップ 飲食コーナー)
熊本県 アンテナショップ 銀座熊本館 Facebook
熊本県アンテナショップ 銀座熊本館のFacebookでは、イベント情報や、入荷品などが写真付きで掲載されています。
https://www.facebook.com/ginzakumamotokan/
熊本県 アンテナショップ 銀座熊本館 スタッフ ブログ
熊本県アンテナショップ 銀座熊本館のスタッフ ブログです。
イベント情報や入荷情報など様々な情報が掲載されています。
http://ginzakumamotokan.blog.fc2.com/
熊本県 アンテナショップ 銀座熊本館 概要
銀座熊本館(ぎんざ くまもとかん)
・住所
東京都中央区銀座5丁目3−16
・交通(最寄駅)
JR 有楽町駅(数寄屋橋方面出口より徒歩5分)
東京メトロ 銀座駅(C2出口より徒歩2分)
・地図
・営業時間
11:00~20:00
・定休日
月曜日
月曜日が祝休日の場合は、営業しています。祝休日となった月曜日の次にくる平日が臨時休館となります。
・TEL
銀座熊本館 事務局
03-3572-1267
熊本県について
熊本県(くまもとけん)は、九州のほぼ中央に位置する県です。
古くから九州の行政、文化、交通、経済の拠点として発展してきました。
肥後(ひご)54万石の歴史と伝統がいたるところに息づき、日本でも有数の文化県として知られています。
世界最大級のカルデラを誇る雄大な阿蘇を含む「阿蘇くじゅう国立公園」、大小120の島々からなる「雲仙天草国立公園」と2つの国立公園を持ち、山あり海ありの、美しい景観に富んだ地形になっています。バラエティに富んだ自然美あふれるロケーションが訪れる人々の心を魅了しています。
相良氏(さがらうじ / さがらし)700年の面影を残す人吉(ひとよし)・球磨(くま)地方や、石の芸術品ともいうべき見事な石橋が点在する緑川流域、不知火海(しらぬいかい)の穏やかな海岸美が楽しめる芦北(あしきた)地方など、見どころは実に豊富です。
また、熊本は水の豊富なところです。環境省選定の「名水百選」に県内からそれぞれ4ヵ所選ばれています。
昭和の名水百選
白川水源、池山水源、菊池水源、轟水源(とどろきすいげん)、「平成の名水百選」水前寺江津湖湧水群(すいぜんじえづこゆうすいぐん)、金峰山湧水群(きんぼうざんゆうすいぐん)、六嘉湧水群(ろっかゆうすいぐん)・浮島、南阿蘇村湧水群(みなみあそむらゆうすいぐん)
人口約74万人の熊本市の上水道を流れる水も、ほぼ100%地下水でまかなわれています。これは全国でも非常に珍しいケースです。この豊かな自然を生かした農林水産業もさかんです。
熊本の四季
南国熊本の新年は、肥後独特の赤酒で屠蘇を祝うことから始まり、各地の神社には一年の息災を祈る大勢の初詣客が詰めかけます。七草、どんどやも終わり正月気分がすっかり抜ける2月になると、400年の歴史を持つ植木市が開かれ、時折寒さがぶり返すものの、人々は早くも春の訪れを感じ取ります。
3月には冬の長い阿蘇にもようやく春のきざしが感じられ、牧草の芽ぶきを促す野焼きが始まります。阿蘇谷一帯で繰り広げられる炎の祭典“阿蘇の火祭り”もこの時期。春の到来を待ちかねた阿蘇の人々の喜びが一気に高まる時でもあるのです。平野部では3月下旬頃から桜も見頃となり、5月にはツツジやミヤマキリシマなどの花だよりが次々と聞かれ、あちこちで花見の宴が催されます。
水ぬるむ季節になると潮干狩りや山菜採りに海山へ出かける人も多く、自然の恵みを満喫する姿が見受けられます。5月の端午の節句にはあちこちの庭先に勇壮なこいのぼりがはためきます。阿蘇杖立温泉郷のこいのぼり祭は素晴らしく、色鮮やかな数千のこいのぼりが泳ぐ様は圧巻です。肥後菖蒲が美しく咲き誇る6月も過ぎ梅雨明けを迎えると、清正公の命日前夜7月23日には本妙寺の頓写会が賑やかに開かれます。8月に入ると夏の三大火まつり(火の国まつり・古墳祭・山鹿灯籠祭)が始まり、真夏の炎のページェントが繰り広げられます。
9月にある熊本市の藤崎八幡宮例大祭は、勇壮な馬追いや武者行列で知られています。この頃から朝夕はめっきりと涼しくなり、秋の気配が感じられるようになります。10月はさわやかな秋晴れのもと、あちこちで体育大会等が開かれ、刈り取られた稲の束が積み上げられた田園風景を目にします。11月になると八代妙見祭の神幸行事(国指定文化財)があり、下旬近くになると南国熊本にも冬の気配が濃くなってきます。
熊本の歴史
熊本県には、カルデラ、豪族の隆盛衰退、蒙古襲来、熊本城築城、天草の乱、明治維新などの歴史があります。
旧石器時代
約27万年前に九州中央部で1回目の大爆発を起こした阿蘇は、その後大規模な爆発を繰り返し、約9万年前の4回目の大爆発で現在の地形がつくられました。阿蘇谷・南郷谷とよばれる大きなくぼ地を阿蘇カルデラ、火山活動でカルデラ中央にできた阿蘇五岳(中岳、高岳、根子岳、杵島岳、烏帽子岳)とよばれる火山群を中央火口丘群、そしてカルデラから四方に広がるなだらかな斜面の山腹を外輪山とよび、これらを総称して「阿蘇山」と呼称しています。
阿蘇北外輪と阿蘇谷が接する“ふち”の部分にある象ヶ鼻遺跡群(ぞうがはないせきぐん)と呼ばれる遺跡からは、今から2~3万年前の旧石器時代の石器が発見されるなど、熊本県内では数多くの遺跡が確認されており、熊本には、約3万年以上前から人々が住んでいたことがうかがえます。
縄文時代
地形的に変化に富む熊本県は、自然環境に恵まれ、草創期から晩期までの遺跡が数多くあります。これらの多くの遺跡から豊富な遺構遺物を発見しています。熊本市の御領貝塚や宇土市の曽畑遺跡などは貝塚として有名です。また、天草市にある椎の木崎遺跡からは、縄文時代中期から晩期にかけての遺物が多量に出土しています。出土した土器は、約3,000~5,000年前に作られた土器と考えられています。しかし、早期の遺構の発見は数が少なく、これは鬼界カルデラ爆発により九州全土が壊滅的に破壊された影響と思われます。
弥生時代
弥生時代には、いち早く稲作が始まり、大陸に近いことから青銅器や鉄器も見られます。玉名市天水町では日本最古の鉄斧が出土しており、弥生文化が栄えたことが知られています。
古墳時代
古墳時代には、まず、宇土半島の基部に4世紀代の前方後円墳が築造され、その後、県内各地で造られるようになりました。このころ、「火の君」と呼ばれる豪族が栄えました。5世紀後半には玉名郡和水町江田船山古墳にみられるように、大陸との交流を示す遺物を持つ豪族も現れました。墓の中に絵や文様を描く「装飾古墳」や石人・石製品を古墳に立てる独自の風習も大流行しました。
筑紫国造磐井の反乱(527年)後、「屯倉(みやけ)」と呼ぶ畿内王権の直轄地が置かれ、全国的な政治体制の中に組み入れられました。
奈良時代
律令時代になると、豊かな熊本県地域は九州で唯一の「大国」となります。鞠智(きくち)城(菊池市、山鹿市)が造られるのもこの頃です。鞠智城は、東アジア情勢が緊迫した7世紀後半に、大和朝廷(政権)が築いた周囲の長さ3.5km、面積55haの規模をもつ山城です。
663年の「白村江(はくすきのえ)の戦い」で唐・新羅の連合軍に大敗した大和朝廷が日本列島への侵攻に備え西日本各地に築いた城の一つで、九州を統治していた大宰府やそれを守るための大野城・基肄(きい)城に武器・食糧を補給する支援基地でした。また、8世紀に編纂された「万葉集」にも熊本の風土が歌われています。
平安時代
平安時代に入ると、肥後国には14の郡とその下には99の郷ができました。荘園全盛期には阿蘇荘や鹿子木荘、山鹿荘など約10の大荘園ができ、武士団が台頭してきました。これが、武士が活躍する時代の始まりでした。
後期では、保元の乱(1156年)後、平家の影響力が強く及び始めました。院政権力と結び、王領荘園の領家や預所職を一族で占め、また受領として国衙の行政権を掌握しました。熊本県やその近郊には平家の落ち人伝説が残っています。
鎌倉時代
鎌倉時代に元軍(モンゴル)が日本を攻めてきました(元寇、蒙古襲来)。そのとき、勇敢に立ち向かった肥後の御家人が竹崎季長(たけざきすえなが)です。下益城郡豊福荘竹崎の生まれの季長は、見たこともない元軍の「てつはう(火薬で爆発する武器)」や毒矢を恐れず、命をかけて戦い、負傷するほど勇戦しましたが、彼に対して、幕府は恩賞を与えませんでした。不満に思った季長は鎌倉まで行って幕府に直訴し、その結果、戦功が認められて、甲佐神社の社領だった海東郡(宇城市小川町東部)の地頭職を獲得することができました。後日、彼が戦っている様子を「蒙古襲来絵詞(もうこしゅうらいえことば)」として描かせ、甲佐神社に奉納しました。「蒙古襲来絵詞」は、当時の武士たちの姿や戦い方を知る上でとても貴重な資料です。
室町時代
熊本県上益城郡山都町には、中世、阿蘇谷・南郷谷を中心に絶大な勢力を誇っていた阿蘇氏(阿蘇大宮司家)の「浜の館」がありました。その後天正14年(1586年)に島津氏から攻められ焼失しました。昭和49年(1974年)に県文化課が行った発掘調査により、建物のほか数棟分の家屋の礎石や庭園などが火災に遭い倒壊したままの状態で発見されましたが、庭園に隠しておいたと思われる祭祀の宝器も発見され、うち21点が国の重要文化財に指定されています。このなかには東南アジアからもたらされた鳥形の陶器もありました。
戦国時代
豊臣秀吉による九州平定後、天正15年(1587年)に肥後国の検地の実施など統治を任されたのが佐々成政でした。秀吉より一揆を起こさせない、検地の3年間禁止などの五箇条の定書を厳命されましたが、領地目録を作成するため検地を要求したため肥後国人一揆が起こり、国内統治に失敗した責任により、成政は尼崎で切腹させられました。
佐々成政の死後、秀吉は肥後を二分し、加藤清正と小西行長に統治させました。肥後の北半分を任された清正は隈本城に入城します。一方の行長は宇土城を拠点に、肥後南部と天草地方の統治を任せられましたが、関ヶ原の戦の際、西軍につき斬首されています。関ヶ原の戦後、功績を認められた加藤清正は人吉・天草を除く肥後一国を与えられました。熊本城の築城や治山治水事業に尽力し、領民の厚い信頼を得た清正は「清正公さん」と呼ばれ、現在でも熊本県民から親しまれています。
江戸時代
慶長17年(1612年)のキリスト教禁止令によりキリスト教徒への弾圧は強化され、天草においてもキリスト教徒に対する迫害は強くなりました。また、寛永11年(1634年)から4年に及ぶ水不足によって飢饉が続き、年貢の取立てが厳しくなりました。こうした不満に立ち上がった農民たちにより一揆軍が組織され、島原・天草一揆が起こります。この一揆軍は当時16歳の少年天草四郎(益田四郎時貞)を一揆軍の総大将として3万7千人にのぼり、富岡城(天草郡苓北町)などの戦いを経て原城(南島原市)に立てこもりましたが、翌年、幕府軍によって原城は落城、内通者であった南蛮絵師の山田右衛門作一人を残し全滅させられました。
乱後、幕府直轄領となった天草には、鈴木重成が荒れ果てた天草を復興させるため、初代の代官に任命されました。重成はキリスト教信仰に拮抗するため、曹洞宗の僧となっていた兄正三を天草に招き、四ヶ本寺をはじめとする多くの寺院を建立し住民の仏教信仰の教化に努めました。また、戦没して無人地帯と化した地域へ、周辺の諸藩からの移民を促進し、復興に尽力しました。天草の貧しさの原因が過大な石高にあると感じた重成は検地をやり直し、石高の半減を幕府に対して何度も訴えましたが、前例がないとして石高半減は認められませんでした。重成は承応2年(1653年)に江戸の自邸で石高半減の願書を残して切腹し、幕府に抗議したと伝えられています。その命をかけた訴えにより、万治2年(1659年)の重成の七回忌に石高軽減が認められました。実際には年貢が半減したわけではありませんが、年貢の見直しの大きなきっかけとなりました。
また、幕末が近くなった文化2年(1805年)、天草で多くの「潜伏キリシタン」が発覚する「天草崩れ」と呼ばれる事件が起きました。島原・天草一揆後も密かに信仰を続けていた4つの村で5,200人もの信者が見つかりましたが、最終的には仏教への改宗と先祖伝来の風習を受け継いでいただけとして誰一人処罰されることはありませんでした。その後も「潜伏キリシタン」として信仰を続けた人々によって、現在も天草地方にはキリスト教文化の名残が多数残っています。
明治・大正時代
明治2年(1869年)の版籍奉還後、同4年(1871年)の廃藩置県により熊本藩は熊本県に、人吉藩は人吉県に、天草は一時、長崎県に編入されるなどしたのち、同9年(1876年)に現在の熊本県になりました。
明治4年(1871年)、熊本医学校、熊本洋学校が設立されるなど、西洋文明による近代化が図られました。一方、士族たちの新政府に対する不満が増大。同9年(1876年)に神風連の乱、同10年(1877年)には西南戦争が起こり、熊本がその主戦場となりました。
水前寺公園の近くに移築されている熊本洋学校教師館は、西南戦争時に佐野常民が博愛社創立の許可を受けたところで、熊本は日本赤十字発祥の地とされています。明治20(1887)年には第五高等中学校が設けられ、夏目漱石、小泉八雲らが教鞭を取り、多くの人材が巣立っています。
また、明治三大築港の一つといわれる三角西港は明治20(1887)年に開港。三池炭鉱万田坑は明治30(1897)年から、同41(1908)年に整備され日本の近代化を支えました。
熊本県紹介Webサイト
熊本県観光総合サイト
熊本県エリア別観光ガイド
http://kumanago.jp/special/e_backno.html
熊本県の温泉
http://kumanago.jp/event/sub/onsen.html
熊本県のグルメ・特産品
http://kumanago.jp/special/product/category.html
熊本県の地域発の観光・イベント情報
http://www.pref.kumamoto.jp/kankou/hpkiji/pub/List.aspx?c_id=3&class_set_id=9&class_id=5869
熊本県の気になる!くまもと
くまもとブランド
取材協力
熊本県 アンテナショップ 銀座熊本館
熊本県東京事務所